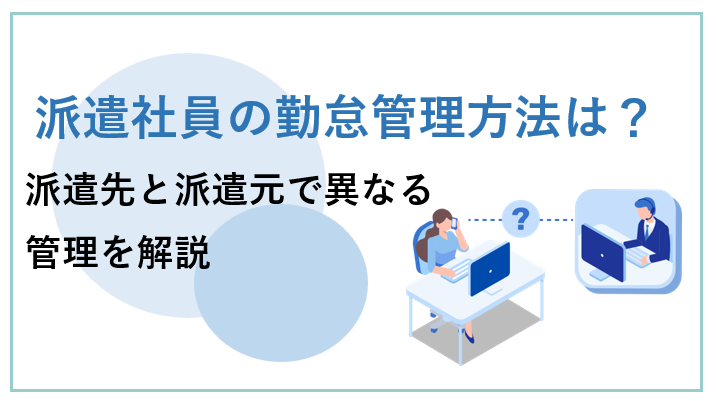振休(振替休日)と代休の違いとは?
給与への影響を解説!

休日と勤務日を入れ替えて働くことを「振替休日」といいます。一方で、休日に出勤した後に別の日を休みにする「代休」とは、仕組みが似ているため、混同しやすいと感じている方も多いのではないでしょうか。
実際には、振替休日と代休では取得のタイミングや割増賃金の扱いに明確な違いがあり、その違いを正しく理解せずに運用すると、労働基準法違反となる可能性もあります。
本記事では、振替休日と代休の違いをわかりやすく整理し、それぞれの取得方法や注意点について詳しく解説します。
1.振休(振替休日)と代休の違いとは?

「振替休日」と「代休」は、どちらも“別の日に休みを取る”制度ですが、定義と仕組みがまったく異なります。この違いを理解していないと、勤怠管理や給与計算のミスにつながり、労務トラブルを招く可能性もあるため注意が必要です。
1.1 振替休日とは?
振替休日とは、もともと休日だった日を出勤日に変更し、代わりに別の平日を休日にする制度です。ポイントは、出勤する前にあらかじめ「振り替える日」を決めておくこと。この手続きが正しく行われていれば、振替後の出勤日は「休日労働」ではなくなり、割増賃金の支払い義務も発生しません。
【例】
日曜日が本来の休日だったが、その日を勤務日に変更し、水曜日を代わりの休みにする。
1.2 代休とは?
代休とは、本来休みだった日に出勤したあと、その代わりとして別の日に休みを取る制度です。出勤したあとに休みを設定するため、その勤務は「休日労働」として扱われます。事前に休日の振替手続きがされていない場合は、代休を与えても「休日に働いた」事実は変わらず、割増賃金の対象となります(詳細は次章で解説)。
【例】
日曜日が本来の休日だったが、その日に出勤し、後日水曜日を代休として休みにする。
1.3 取得タイミングの違い(事前か事後か)
振休と代休の最大の違いは、「休みの日をいつ決めるか」にあります。振替休日は事前にスケジュール変更を行うのに対し、代休は事後対応です。この違いが、割増賃金の有無や勤怠の扱いに直結します。
2.割増賃金の扱いと給与計算への影響

2.1 振休と代休における賃金の違い
振休の場合
事前に休日と平日を振り替えていれば、もともとの休日は「通常の労働日」として扱われるため、休日労働ではなく、割増賃金の支払いは不要です。ただし、時間外労働や深夜労働が発生した場合は別途割増対象となります。
代休の場合
事前に振り替えていなければ、その休日出勤は「休日労働」として扱われます。特に法定休日に出勤した場合は、代休を与えても割増賃金(35%以上)の支払いが必要です。これは労働基準法により定められており、代休の取得だけでは割増賃金の支払い義務を免れません。
【ポイント】
振休は給与に影響が少ない。
代休は休日出勤として給与の加算が必要。
2.2 法定休日・法定外休日との関係
休日には、「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」があります。これらの違いによっても、給与計算の方法や割増賃金率が変わります。注意が必要なのは「週40時間(または1日8時間)を超えた場合」です。つまり、所定休日労働=必ずしも割増なし、ではなく、週の総労働時間の上限とセットで考える必要がある点に注意しましょう。
法定休日
会社が週1回以上設けなければならないと定められた休日です(労働基準法35条)。この日に出勤すると、最低でも35%の割増賃金が必要になります。
法定外休日(所定休日)
法定外休日(所定休日)とは、就業規則などで会社が独自に定めた休日で、労働基準法で定められた法定休日(日曜など)以外の休みを指します。この日に出勤しても、その日の労働時間が8時間以内であれば「休日労働割増(35%)」は発生しません。
【例】
日曜を法定休日とする会社で「土曜を所定休日」としている場合、月〜金で40時間勤務していれば、土曜の労働はすべて時間外労働扱いになります。
【ポイント】
週の労働時間が40時間を超えれば、その分は時間外労働となり、25%以上の割増賃金が必要になります。
3.振替休日・代休導入時の注意点
〇就業規則への明記の必要性
振替休日を導入する場合は、就業規則にその制度を明記することが推奨されています。ルールが決まっていないまま運用を始めてしまうと、従業員との間でトラブルが起きたり、最悪の場合は振替が無効とされて割増賃金の支払いを求められる可能性もあります。
就業規則には、法定休日や所定休日のほかに、「休日を他の労働日に振り替えることがある」ことも記載しておきましょう。こうした取り決めがあることで、制度を正しく運用するための根拠になります。
また、就業規則に定めがない場合でも、労使協定を結べば振替休日を付与することは可能です。ただし、代休制度と併せて取得条件や期限、賃金の扱いもルール化しておくと、より安心して制度を運用できます。
〇取得期限や運用ルールのポイント
振替休日は事前に休む日を決めておく必要があり、基本的には同じ給与締め期間内に取得するのが一般的です。締日をまたぐと「賃金全額払いの原則」に反する可能性があるため、一度は休日出勤分の給与を支払い、振替後に控除で調整する対応が必要になります。
また、週をまたいで振替を行うと、週40時間を超える勤務となり、時間外労働として割増賃金が発生するケースがあります。たとえば平日に40時間働いたうえで土曜も出勤した場合、超過分に対して割増賃金(通常25%)を支払わなければなりません。
なお、事前に振替日を決めていない状態での休日出勤は「振替休日」ではなく「代休」となります。代休は休日出勤後に取得する休みであり、未消化のまま放置すると法令違反につながるおそれがあるため、早めの取得と管理が重要です。代休を取らない場合は、割増賃金を支払う義務があります。
4.よくあるトラブルとその回避策
〇「振替休日ではなく、有給休暇で休みたい」と言われた
「振替休日ではなく、有給休暇を使いたい」と従業員に言われることがあります。この場合、振替休日は給与の支払いが不要なのに対し、有給休暇は有給=給与が発生します。つまり、会社側は人件費を抑えたい、一方従業員は収入を減らしたくない、という思惑がぶつかることでトラブルに。
就業規則に振替休日の記載がなければ、従業員に強制はできません。無理に休ませると「労働の権利を奪った」と判断され、給与の支払い義務が発生する可能性もあります。このようなトラブルを防ぐには、就業規則に振替休日のルールを明記しておくことが大切です。
〇振替勤務で8時間を超えた
振替勤務でも1日の実働が8時間を超えた場合や、週40時間を超えた場合は、時間外労働として割増賃金(25%)が必要です。休日の振替だからといって、割増が不要になるわけではないので注意しましょう。
〇忙しくて振替日が決められない
繁忙期などで事前に振替日を決められない場合、対応が遅れると振替休日が長引き、管理が難しくなります。
このようなケースでは、あらかじめ就業規則に「振替休日は1か月以内に取得」などのルールを定めておくとスムーズです。また、どうしても休みを決められない場合は、休日手当で対応することも可能です。
5. まとめ:振休と代休を正しく理解し、適切な勤怠管理を行いましょう!
振替休日と代休は似ていますが、運用ルールや賃金の扱いが異なります。
振替休日は「事前に休日と勤務日を入れ替える制度」で、原則として休日手当は不要です。ただし、週40時間を超えるなどの場合は割増賃金が必要になることがあります。
一方、代休は「休日出勤の代わりに後日休む制度」であり、出勤した日の分は休日手当として割増賃金を支払う必要があります。たとえ代休を与えても、その分の給与を免れることはできません。
それぞれの制度を正しく理解し、就業規則での明確なルール化や、36協定の締結など必要な手続きを行ったうえで、適切に勤怠管理を進めましょう。